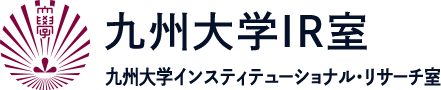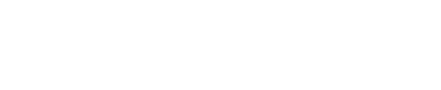九州大学インスティテューショナル・リサーチ室(IR室)は、エビデンスに基づいた大学の改革・改善を支援する組織として、平成28年4月に設置されました。それまでは、「国立大学法人評価」や「大学機関別認証評価」等の大学の諸活動の自己点検・評価業務を中心とする大学評価情報室として活動してきましたが、自己点検・評価の結果を分析し、数値指標やエビデンスを伴った定性的な指標に基づいて、大学の運営や経営を戦略的にマネジメントできるガバナンス体制を強固にするべく、総長のリーダーシップの下、IR室が設置されました。
国立大学法人ガバナンス・コードや第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱においても、エビデンスによる意思決定・法人経営が重要視されており、エビデンス、すなわち「客観的かつ精査された説得力のあるデータ」に基づいて改革・改善の方針を示すことによって、大学の構成員がその必要性を共通に理解でき、合意形成も進むと考えられます。
このような観点から、IR室の最も重要な任務の一つは、「客観的かつ精査された説得力のあるデータ」を集積することです。これまで大学の各部署には、多種多様で膨大な数のデータが蓄積されてきましたが、それは担当部署(時には担当者)が最も収集しやすい形、利用しやすい形、あるいは提出先の要求に沿う形などで集積されたものでした。さらには、同じ種類の同じ期間を対象にしたデータであっても、データの定義が異なる場合も少なくありません。このような状況下では、単にデータの提供元からIR室が収集しただけでは、「客観的かつ精査された説得力のあるデータ」にはなり得ません。IR室では、各部署の尽力のもとで、学内に散在するデータを「客観的かつ精査された説得力のあるデータ」にするべく集積を実施しています。一方で、データの情報公開には格段の留意が求められ、この点についても、公開範囲の区分を精査し、データの集積元とも協議をしながら区分けを進めています。
「客観的かつ精査された説得力のあるデータ」が集積できれば、次の段階は、大学の改革・改善の支援となるデータへの転換です。集積されたデータの経年変化、部局間・大学間での比較、各種データの掛け合わせ(例えば、財務情報×研究情報、研究情報×教育情報、教育情報×国際情報など)とそれに基づいた分析によって、大学運営の意思決定に資するデータとなりえます。
このような考えを踏まえ、IR室設置後最初の2年間では、IR室活動体制の構築(データ集積・公開など)、IR関連システムの整備(データ項目見直し、外部データ連携など)、研究分析ツールの導入と利用促進を3つの柱として取組み、IR活動の基盤の構築を行いました。
その後は、執行部へ大学運営の意思決定に資するデータの提供として、次の活動を行っています。1つは、本学の重点施策(指定国立大学法人構想や中期目標・中期計画など)で掲げられた成果指標(KPI)を多面的な切り口で可視化し、進捗状況および達成予測について報告すること、もう1つは、重点施策を実施するにあたり、より強固なエビデンスに基づき明確な方向性を示すために、テーマを定め、学内より集積したIRデータを集中的に分析し、その結果より得られる本学の特徴や強み・弱みに関する情報を提供することです。このほか、学内の教職員に対しては、学内にある各種データをデータリストとして提供するとともに、各種IRシステムのマニュアルやグッドプラクティスを整備・提供しています。一般の皆様に対しては、IR室で集積したデータを活用し「FACT BOOK」として本学の情報を経年で可視化・公開していますし、海外の研究者や学生が本学との共同研究や留学先の検討に活用できるよう、本学と各国間の共著関係や留学状況を世界地図上に表した「グローバルエンゲージメント」も公開しています。
IR室がなすべき大学改革・改善の支援のための意思決定に資するデータ提供機能を充実させるためにも、皆様方のご支援、ご協力をお願いする次第です。
令和6年10月
九州大学 理事・副学長(評価・IR担当)
IR室長 内田 誠一